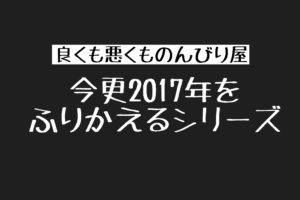鹿児島市にあるTATEBA BLDGにて開催された「ZINE FEST 遊本祝祭」に出展したZINE『ONESELF Lab』第一幕 自分を考える の原稿です。
初めてつくったZINEの最初の本編ページということで、ブログのONESELF Labにも置いておこうと思います。
(めっきり更新が滞り、ごめんなさい。また、ここからスタートしていきます)
ーー
母ひとり、子ひとり。
「夜で、雨が降ってたよ」
小学生の時、自分の産まれた日について母に聞いたことがありました。
確か、調べ学習のひとつだったと記憶しています。今思えば、複雑な家庭環境の子もいただろうに、まあまあ攻めた宿題でした。
わたしは、母が三十歳前半で産んだ子どもです。
出産予定日を過ぎてもなかなか出て来なかったことを例えに「かざりちゃんは、のんびり屋さんだよね」と大人になった今でも時々言われます。
幼い頃はそれなりにムカついたりもしましたが、今はそれも愛なんだと受け止められるようになりました。
父は間に合わず、出産は母一人。
心細かっただろうに、雨の降る夜、のんびり屋さんの赤ちゃんを、そこそこ安産で誕生させてくれました。
「花咲里(かざり)」という初見ではまず読まれない名前は、父がつけてくれました。
はじめは「花坐里」だったものの、出生届を提出する役場の窓口で「人の名前に仏教の文字は使えない」と却下されてしまったそうです。
この話しを父から電話で聞いた時、「なんで、坐を使いたかったの?」と尋ねると、「三文字が七画ずつになるから」と答えられ、「パチンコか?」と妙な気持ちになったことは父には言いませんでした。
名付けられた身としては、今の「花咲里」の方が圧倒的に気に入っています。
字面が美しいし、人に説明する時も「花が咲く里って書いて、かざりです」と説明しやすい。
坐のままだったら、なんて説明してたんだろう。
「花に坐禅の坐に、古里の里です」って言ってたのかな。
今の名前の方が良いです。珍しいけど、しっくりきてます。保育園生ぐらいまではその名の通りに育ち、将来の夢は「お花屋さん」でした。
すてきな名前がつけられ、穏やかな暮らしが待っていそうな雰囲気ムンムンですが、三年後に両親、離婚を決意。
そして、実行。
とはいえ、わたしには伝えられず、父は単身赴任だと聞かされていました。
その期間、約七年。事実が判明したのは、十歳の夏。母と二人で出かけた旅行先でした。
小学生時代、夏休みの終わりに宮崎のフェニックス・シーガイア・リゾートに行くのが定番でした。
母の運転する車で二時間ぐらい。一番の目的は、巨大プールのオーシャンドーム。
今はもう閉業してしまったけれど、幼い頃の楽しい思い出が詰まった大好きな場所でした。
十歳になる年までは。
当時、世界最大級の屋内プール施設だったこともあり、いつも芋を洗うぐらいの人がいました。
その合間を縫うように、浮き輪を使って波が出るプールや流れるプールでプカプカと浮かぶわたし。
基本的にはひとりで遊び、母とは時々合流。そうとう自由な時間を過ごしていました。
覚えているのは、飲食店の椅子に座って待つ母の背中。
ぱっと見は普通だけど、違ったのはその雰囲気。妙に暗い空気が漂っていて、「怒ってるのかな」と内心ビクビクしながら向かい側の席に座りました。
ふりかえると、我が子に深刻な話しをする決意を固めた大人の背中だったと思います。
恐ろしさをまといながら切ない雰囲気も持ち合わせていましたから。
そうして告げられたのは、離婚の事実。
言いにくそうに、でもハッキリと伝えられました。
瞬間、湧き上がった正直な気持ちは「今まで騙してたんだ……!」という衝撃と怒り。
三歳の離婚を、七年後に打ち明けられて「そうだったんだね。お母さんも大変だったね」と言えるほど出来た十歳ではありませんでした。
また、不思議と腹が立ったのは目の前の母に対してで、父には特に何も思いませんでした。
親権を取得して実家に戻り、祖父母と一緒にわたしを育てている母には感謝こそすれど、恨む理由は無い。
むしろ、離れて暮らす父に対して怒りを抱く方が当然のように感じますが、あの時の自分はずっと一緒にいた母が自分に対して嘘をつき続けていた事実が、なにより悲しかったのです。
真夏のオーシャンド―ムの一角で涙する親子の姿は、かなりドラマチックだったと思います。
ドキュメンタリー映画のようでもあったでしょう。母の泣き顔、子どもの腫れた目。
頬を伝うものは同じだったけれど、気持ちは少しズレていました。そうして出てしまいます。後悔の言葉。
「騙していた分、お金で返して」
傷ついた心から出たそのままの言葉だから、大人になった今もよく覚えています。心の奥底から出た言葉でした。
しかし、時が経つにつれて母の苦労を理解できるようになり、愛されている今を信じられるようになっていく。すると、出てくる気持ちは、後悔です。
「どうしてあの時、あんなことを言ってしまったんだろう」割れたお皿が元に戻らないように、放ってしまった言葉は無かったことにはできません。
後悔を抱いて数年後、「このまま母が死んだら、それこそ一生後悔する」と思って、二十歳を過ぎたある日、母が運転する車の助手席で勇気を振り絞って口にしました。
「あの時はごめんなさい」
母から返ってきたのは、「そうだっけ?」ぐらいの反応。意を決して伝えたわたしは拍子抜け。
言いにくかった謝罪だったけれど、あれぐらいで収めてくれた母の愛だったのかも。
真実は、母のみぞ知る。